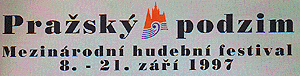プラハの9月はまだ音楽に関していえばプレシーズンだ。ブルタヴァ川沿いにある「芸術家の家」のチケット売場にいると9月末から始まるチェコ・フィルの秋シーズンのチケットの受け取りにやってくる市民をちらほら見かける。一方で観光客相手に市内の数多くの教会で開かれるミニコンサートやリサイタルには夏からこの季節にかけて毎晩ことかかない。教会という音場で聞くことができるパイプオルガンの響きは自分が今ヨーロッパに来ていることを改めて実感するのに十分だ。
プラハには「プラハの春」という国際音楽祭(旧ソ連軍が進駐した事件じゃなくて)があり、毎年スメタナの「我が祖国」をチェコフィルが演奏するのも有名だけど、9月、音楽の秋シーズンの前に「プラハの秋」というこれもまた国際音楽祭が催される。「プラハの春」よりはずっと小規模だしチェコフィルの出番もたいていの場合ないみたいなのだが、私がプラハを訪れた頃はちょうどその音楽祭の期間だったのでいくつかチケットを買って行ってみた。
パリでコンサートへ行ったときもそうだったけど、日本で行われるコンサートと違って開演時間はちょっと遅め。それなりにドレスアップした人もいれば、いかにも旅行者といった感じの人もいてさまざま。日本人もまとめてけっこう見かけた。プログラムの冊子を買おうとしたらおばさんが、英語のはないよと言ってくれるが、別にかまわないのでそのまま買う。ファンファーレで開演が伝えられ、いかにも音楽祭らしくてうれしくなる。休憩時間には40Kcvほどでゼクトが飲めるし(うーん、これについては日本でもコンサートの合間にジュースとコーヒーだけでなく、シャンパンも飲めるような時代になるのはまだ先なのだろうか。華やかな感じにもなるのになあ。)
チェコフィルが出てこないかわりにプラハ放送交響楽団だとかスロバキアフィルだとか、普段なかなか聴けないオケの演奏を聴いてこれた。プラハ放送など、放送局のオケらしくなかなかしっかりと音楽を聞かせてくれた。一つだけがっかりしたのはチャイコフスキーの「悲愴」の3楽章が終わった後に拍手が...
っていう場面かな。あらら、そういうこともあるのね、ヨーロッパでも。全曲終わった後の拍手が慎重になってなかなか出なかったのも、なんだかなあ。でもここの「芸術家の家」の大ホールも音響的にはなかなか。低弦も嫌みなく音が通って良かったと思うよ。ただし、二階席で大きな大理石の柱の後ろにも客席があって、ありゃないと思うな。そこに座っていた人はステージが半分も見えないんじゃないかなあ。彼は2曲目から席を移動してしまったのを見かけたけれど。安い席でいいやと2階席を買う方は配席図を確認してね。
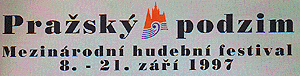
Photo: Rudolfinum,
Sep/97
|